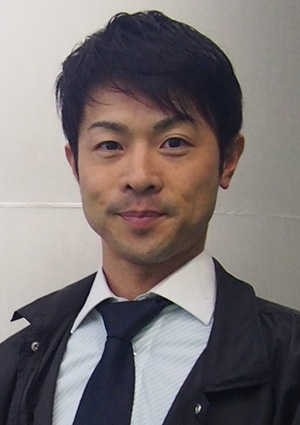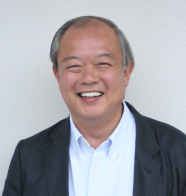若狭ソーシャルビジネスカレッジとは
社会は、常に変化をし続けて、いまの私たちがあります。
しかし近年は、社会もそれを取り巻く自然環境も、変化の幅と速度が増していて、将来に対しても漠然とした不安を抱いてしまいます。
それでも、自分の大事なことを見失わず、その変化に柔軟に応じていくことで不安は希望に変わるのではないかと思っています。
変化に流されるのか、反発するのか。白か黒かではなく、しなやかにたくましく生きていく力を養うことで、今度は自分たちから変化を起こしていくことができるかもしれません。
私たちのいる若狭はごく普通の“田舎”です。
でも、自分の生き方や、地域のあり方を考え、実行に移してみる場として、田舎はとてもチャンスが多いところです。
このカレッジでは、これからの一人一人の幸せ、地域、社会全体の幸せについて共に考え、実現に近づけられるような場にしていきたいと考えています。
-
こんな人に
-
- 地域の課題解決やソーシャルビジネスに関心がある人
- Uターン、Iターンなど、今後田舎で暮らしたい人
- 「半農半X」な暮らしに関心がある人
- 田舎に興味があり、何かできないかと考えている人
- 共に考え、行動できる仲間を求めている人
カリキュラム
フィールドワークと座学で、五感を使って地域に触れ、参加者と地元、講師陣が交わりながら、「これから」について共に考える場にしていきます。第2回は澁澤寿一氏、第4回は塩見直紀氏(半農半X研究所)を特別講師としてお招きします。また各回、農業、漁業、観光業をはじめ、地域で活躍する地元講師陣を予定しています。
なお、カレッジの修了生を対象に、移住や就職・起業の個別支援を実施しています。
また、座学ではリモート参加にも対応いたします。
参加をご検討の方は、事務局へお問い合わせください。
-
第1回
9月3日(日)
自然をフィールドにする生業-アウトドアアクティビティの体験・企画
-
第2回
10月1日(日)
地域を知る-地元学
-
第3回
11月5日(日)
地域の人の想い・暮らしを知る-聞き書き
-
第4回
12月3日(日)
自分を知る-セルフデザインワークショップ
-
第5回
1月14日(日)
今の地域を知る-地元で活躍する方への取材
-
第6回
2024年3月3日(日)
活動報告会
スタッフ・講師
若狭ソーシャルビジネスカレッジ実行委員会 代表
田辺一彦
(一社)若狭路活性化研究所 代表理事、(有)湖上館パムコ 代表
地元若狭で、カヤックツアー、サイクリングツアー、小学生対象のキャンプなど、20年ほど若狭の自然を活用し、自然と人をつなぐ取り組みを行ってきた。また、2012年より地域のにぎわいを復活させようとサイクリングイベントやトレイルランニング、オープンウォータースイミングなどのイベントを実施し毎年参加者は年間約4000人を超え、自然を活用したスポーツによる観光を実践してきた。2014年より(一社)若狭路活性化研究所を地域の有志とともに設立し、これらの事業を通じた若手の人材育成にも取り組んでいる。
(一社)若狭路活性化研究所
(有)湖上館パムコ
特別講師
澁澤寿一
NPO法人共存の森ネットワーク理事長 農学博士
1980年国際協力事業団専門家としてパラグアイ国立農業試験場に赴任。帰国後、長崎オランダ村、循環型都市「ハウステンボス」の役員として企画、建設、運営まで携わる。
現在、共存の森ネットワーク理事長として、全国の高校生100人が「森の名手・名人」や「海・川の名人」をたずねて聞き書きし発信する「聞き書き甲子園」の事業や「豊森なりわい塾」「石徹白カレッジ」など、森林文化の教育、啓発を通して、人材の育成や地域づくりを手がける。福井県「里山・里海湖研究所」アドバイザー。岡山県真庭市では1998年から木質バイオマスを利用した地域づくり「里山資本主義」の推進に努める。
NPO法人共存の森ネットワーク
事務局
福島空
宮城出身。全国の農山村の地域づくりに携わる。2014年より福井に移住。現在、若狭路活性化研究所および(有)湖上館パムコにて、若狭の自然を活用したイベント、ツアー、子どもから大人までの人材育成に関わるプロジェクトを進行中。
若狭のこと

福井県南部にある若狭町は、山も海も身近にあり、ラムサール条約にも登録された三方五湖という湖もあり、豊かな自然環境に恵まれています。
海や湖での漁業、梅をはじめとした農業、そして観光業でかつては賑わった地域ですが、現在は担い手不足等、地域で抱える課題は少なくありません。その解決策のひとつとして、行政・民間・地元住民による就農定住支援施設「農楽舎」をはじめ、積極的な取り組みも行われており、県外からの移住者も少しずつ増えています。